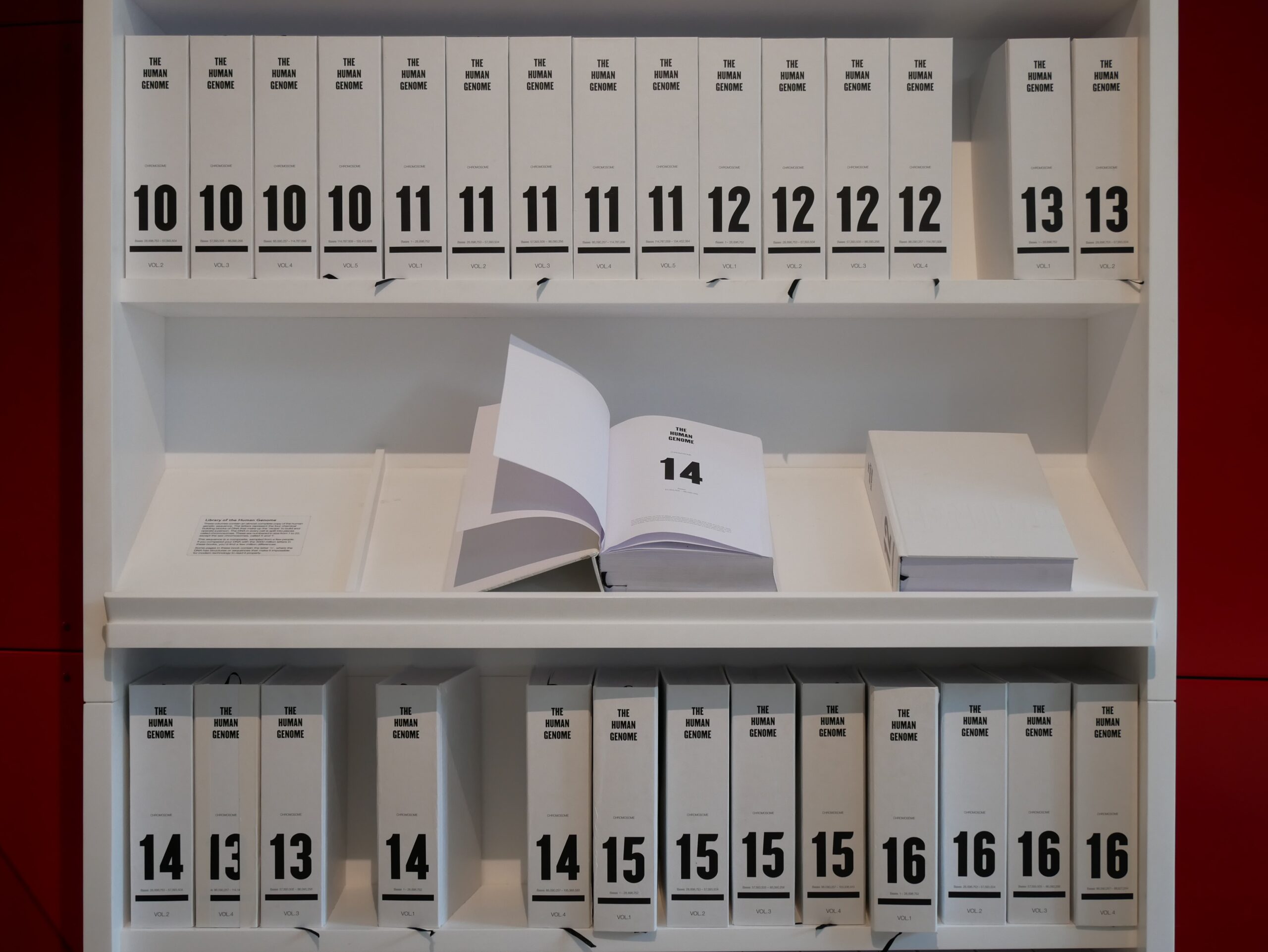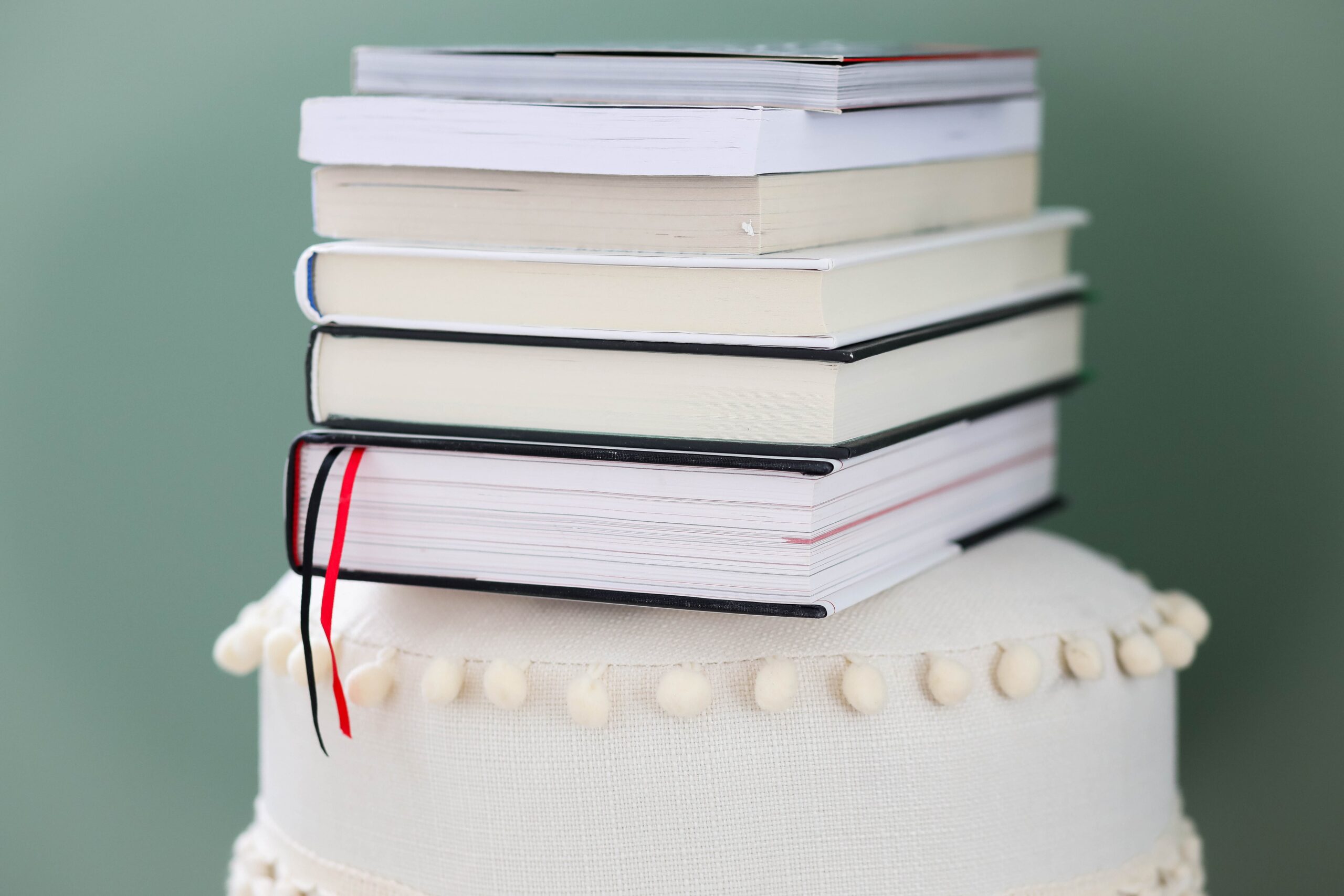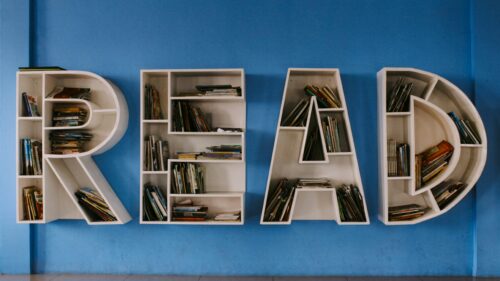中学受験で、東京男子御三家を含む鉄緑会指定校に複数校合格し、サピックスを経て受験した中学校全てから合格をいただきました。
受験も終わったこの時期、幼児期に取り組んだ知育の遊びを振り返ってみました。
たくさんの知育玩具を購入しましたが、特によく遊んだものをご紹介します。
アナログだけど、しっかりと考える力(思考力)がつくおもちゃです。
頭のよくなるゲーム『アルゴ・algo』 学研

アルゴは、大道芸人としても有名な数学者・ピーター・フランクル氏ら算数オリンピック委員会の方が中心となって発明・開発したゲームです。
簡単にルールを言うと、伏せてあるカードに書かれた数字を推理して当てていくというゲームです。
自分の手持ちのカードを短期記憶として覚えておくのと同時に、自分のカードを元に相手の手持ちのカードを推理していきます。
実は、中学受験が終わった後も
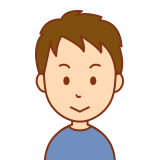
ママ、アルゴやろう~
と誘ってきます。
何がそんなに魅力なの?って聞いたところ、
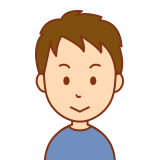
うーん。とにかく全部!
アルゴは面白いからほんとに。
確かに、単純ゆえに思考力勝負というシンプルなゲームですが、やってみると奥が深いです。
対象年齢が6歳から大人までとありますが、数字の11までわかるお子さんでしたら、6歳以下から楽しめますよ。
結構、大人も簡単に負けてしまいます!
暗記力と同時に思考力が鍛えられるゲームです。
どうぶつしょうぎ

今は本格的な将棋を楽しんでやっていますが、将棋の導入としてどうぶつしょうぎで遊んでいました。
可愛い動物が描かれたコマ8個を12マス内で動かす、ボードゲーム風になっています。
自宅でお友達と遊ぶ時も、ルールが単純なので、すぐに一緒に遊ぶことができますよ。
たんぐらむ・タングラム

三角や四角の木製のピースを組み合わせて、形を平面上に作っていきます。
どのピースを使えばいいか、平面図形の能力を養えるゲームです。
中学受験の平面図形では、ここに一本線を引くと解法への道筋が見える、ということが多々あります。
図形を色んな切り口で、とらえることができるゲームです。
また、タングラムは、相手と競ったりするゲームではないので、じっくり自分のペースで取り組むことができるのが良いです。
これも本当によく遊びました。
まとめ

子供が小さい時って、お勉強ぽくないゲームで、何気に思考力を養っていくことが大事かな、と思います。
小さい時は、脳がどんどん大きくなり発達していく時期ですから、良さそうなものは色々と取り入れていました。
そんな中でも、遊んで良かった知育玩具3点をご紹介しました。
さて、子供たちが小さい時は、知育玩具のサブスクサービスはなかったのですが、最近は手元にいろいろなおもちゃが届くサービスがありますよね。
良いと思って購入しても、子供は興味を示さないということもあったので、サブスクで試してから気に入ったものを購入ということができれば、もの増えないのでいいですね!
特に、cha-cha-chaは、大人気のボーネルンドやエドインターなど良質なおもちゃを主に取り扱っているようですよ。
今子供たちが小さかったら、こちらのcha-cha-chaを迷わず頼んでいると思います。